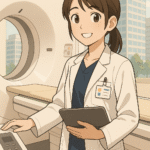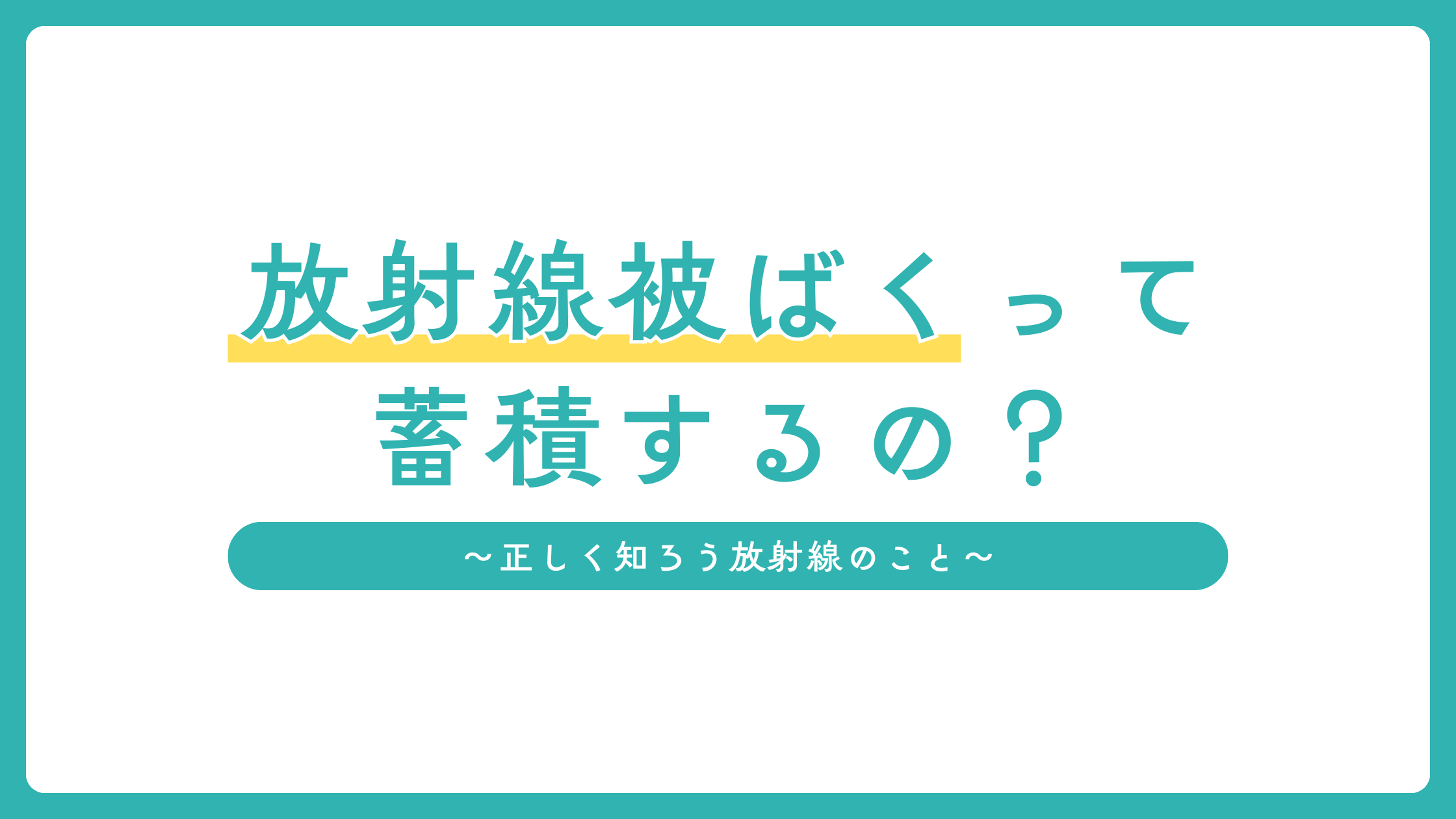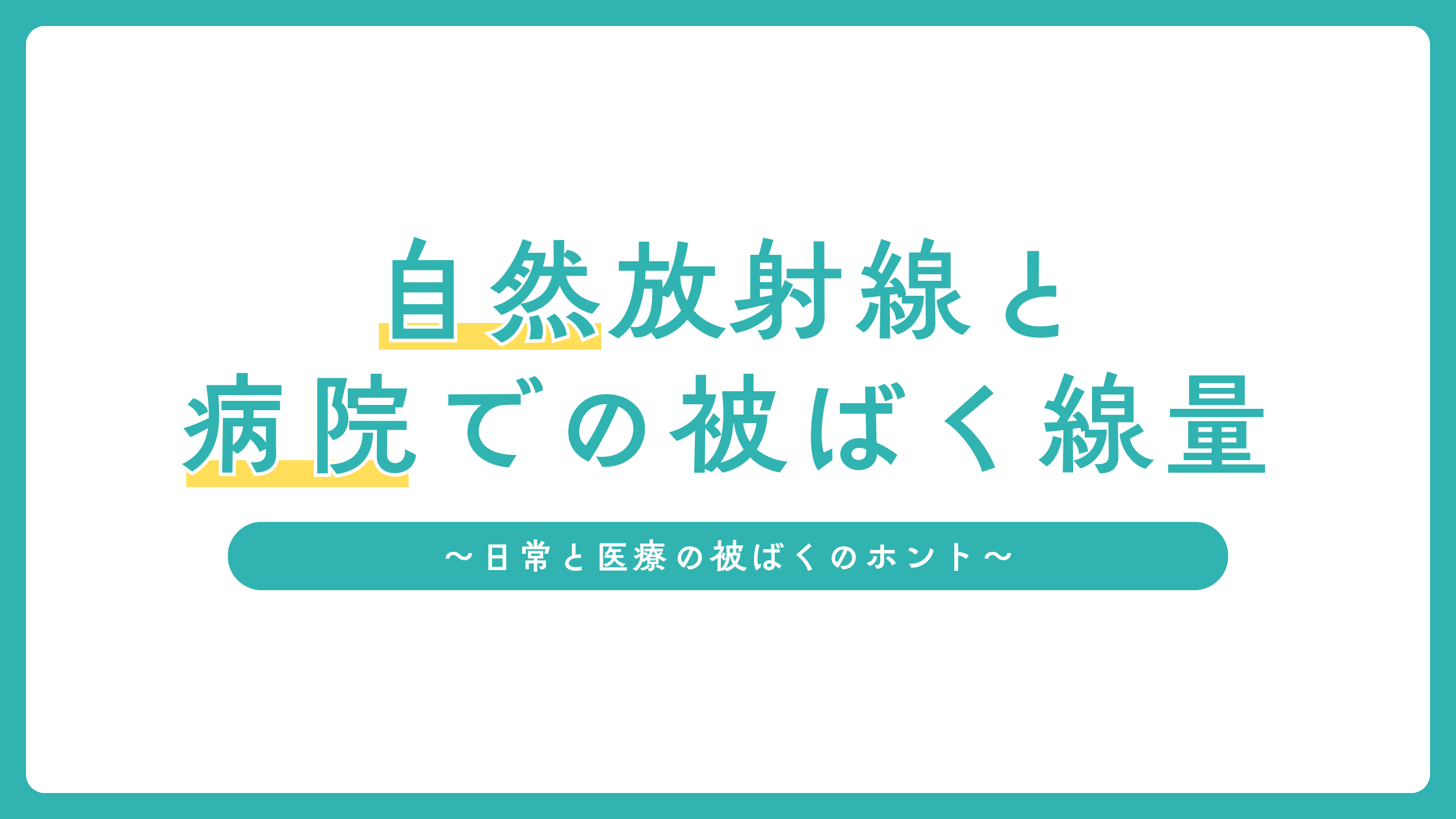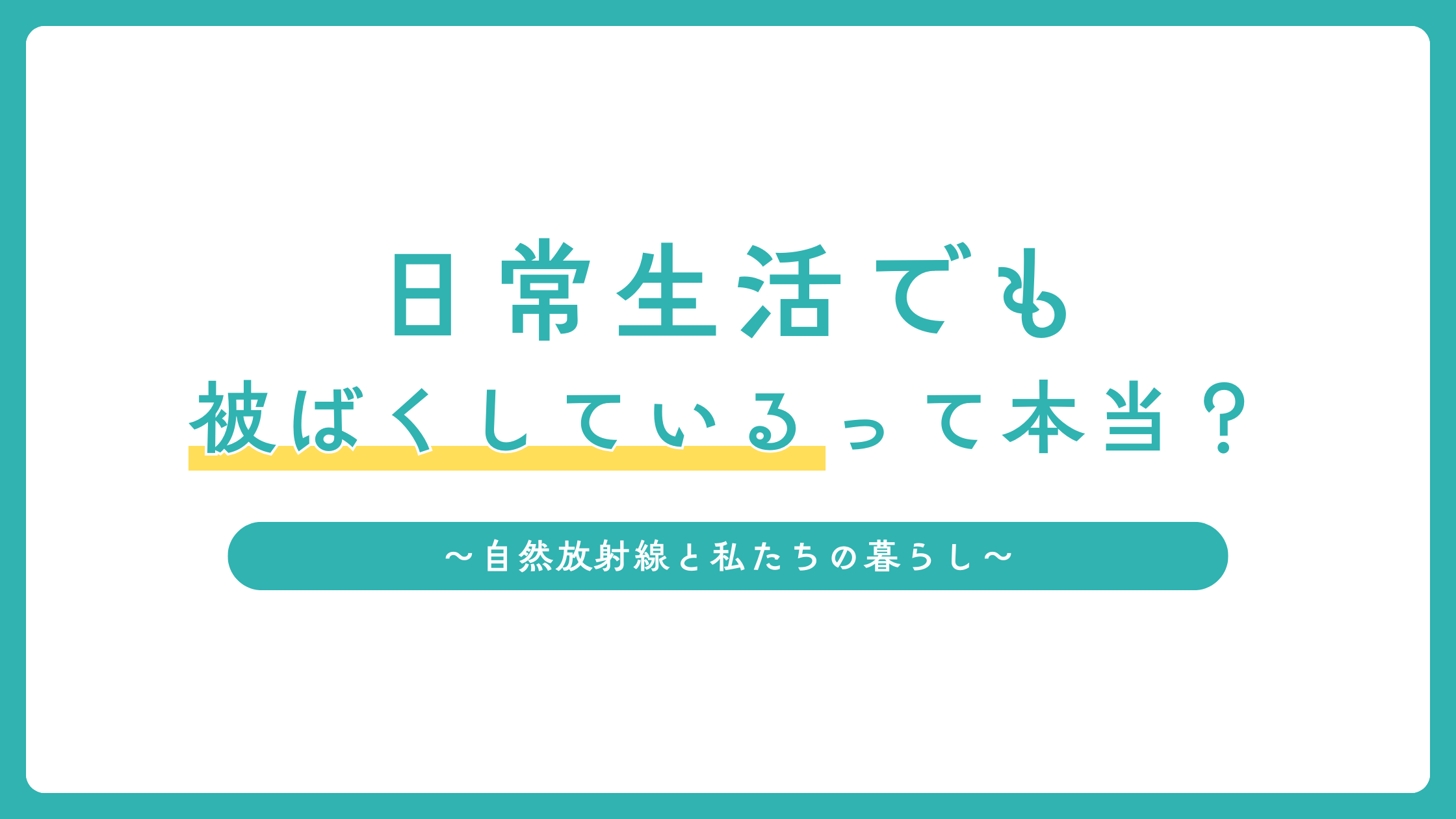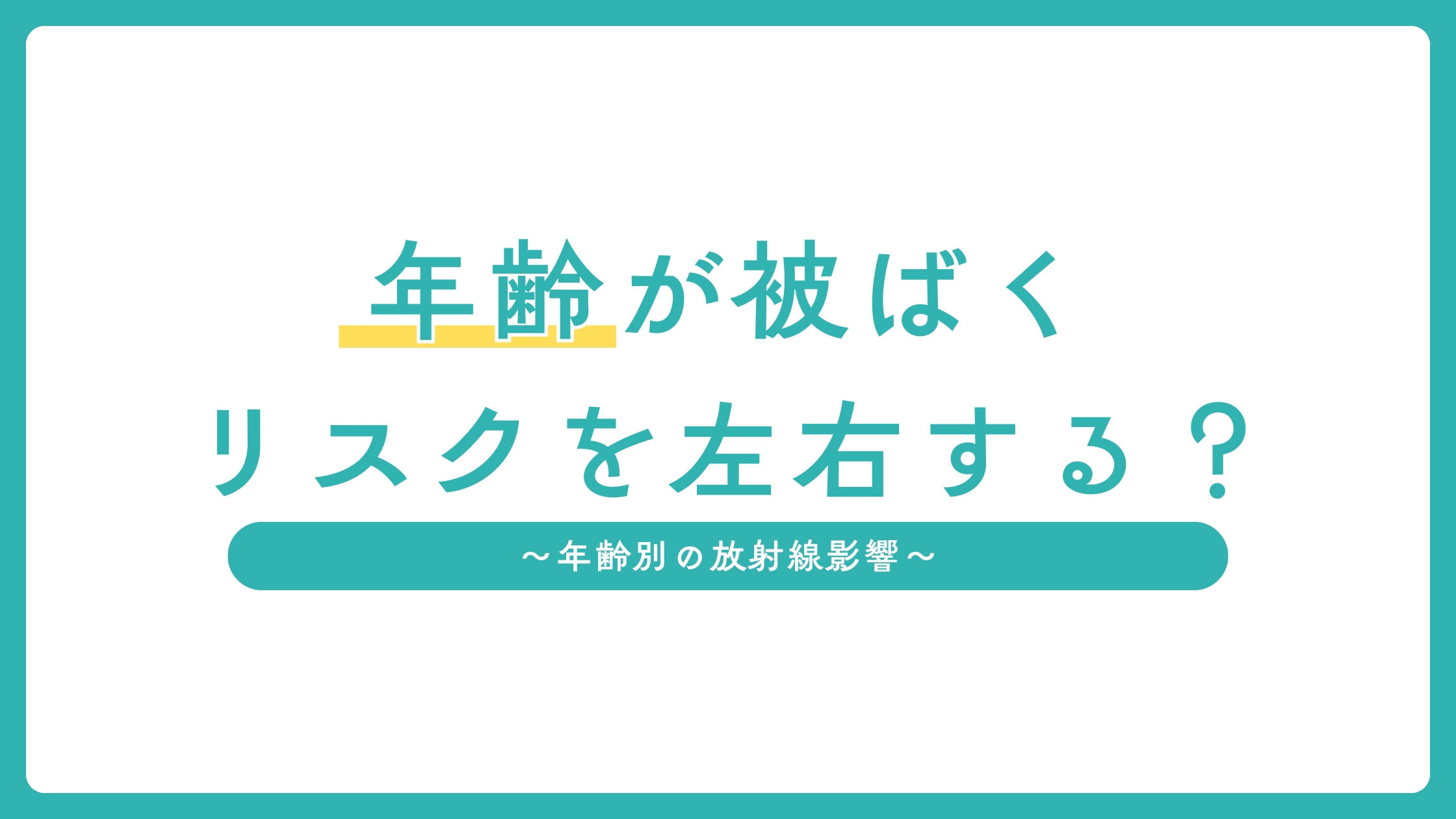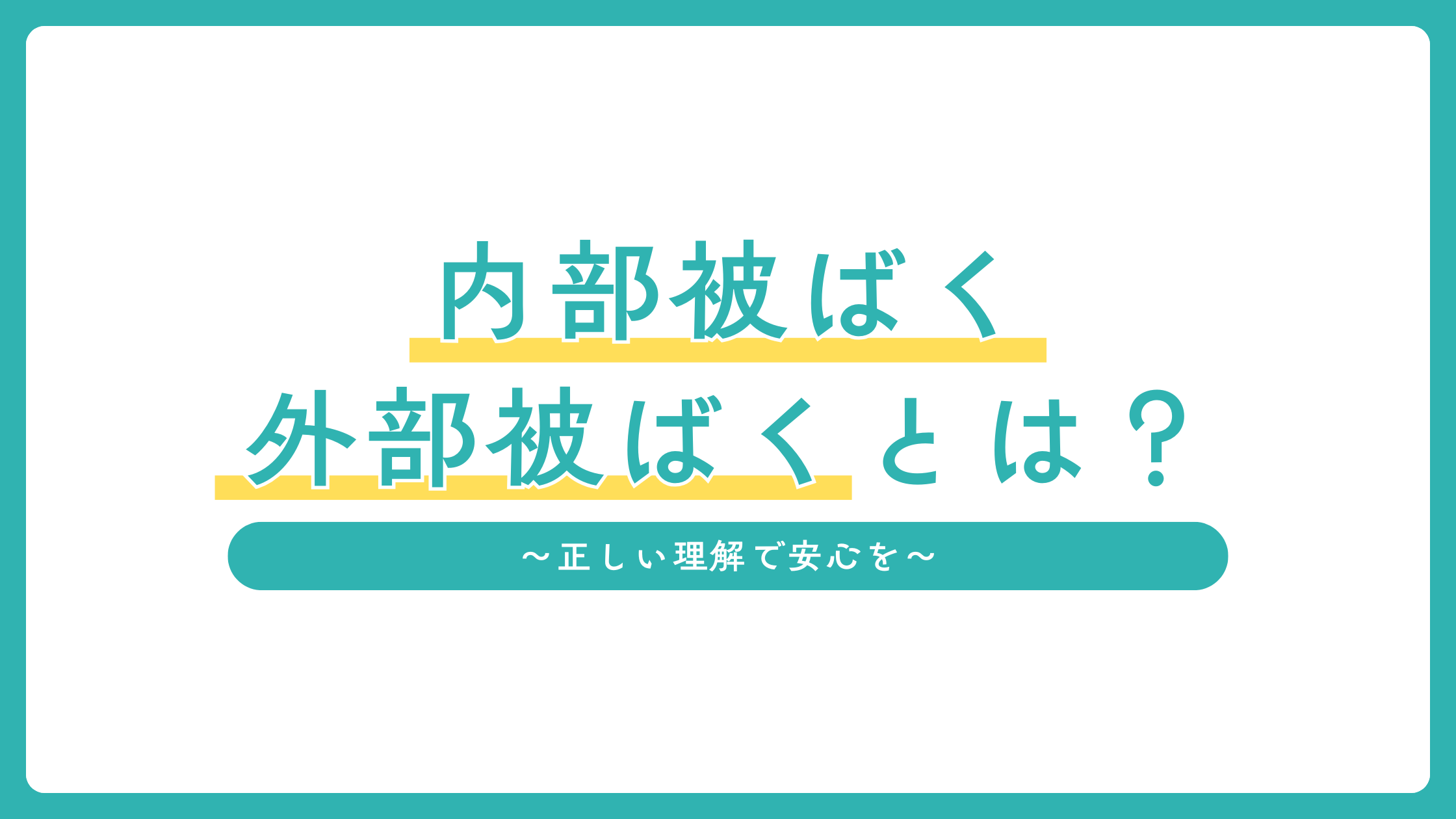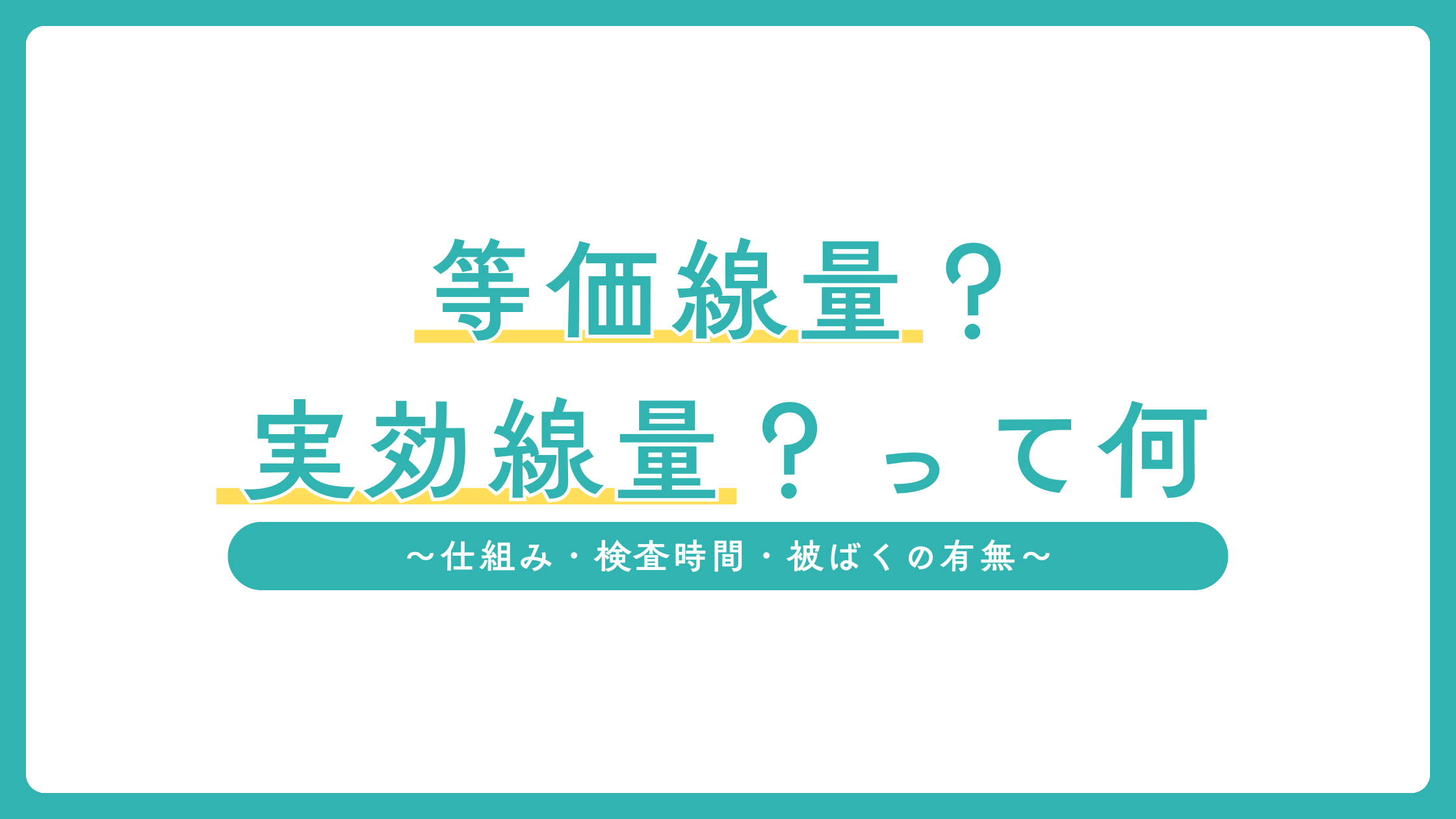ALARA(アララ)の法則とは?放射線を安全に使うための基本原則を放射線技師が解説
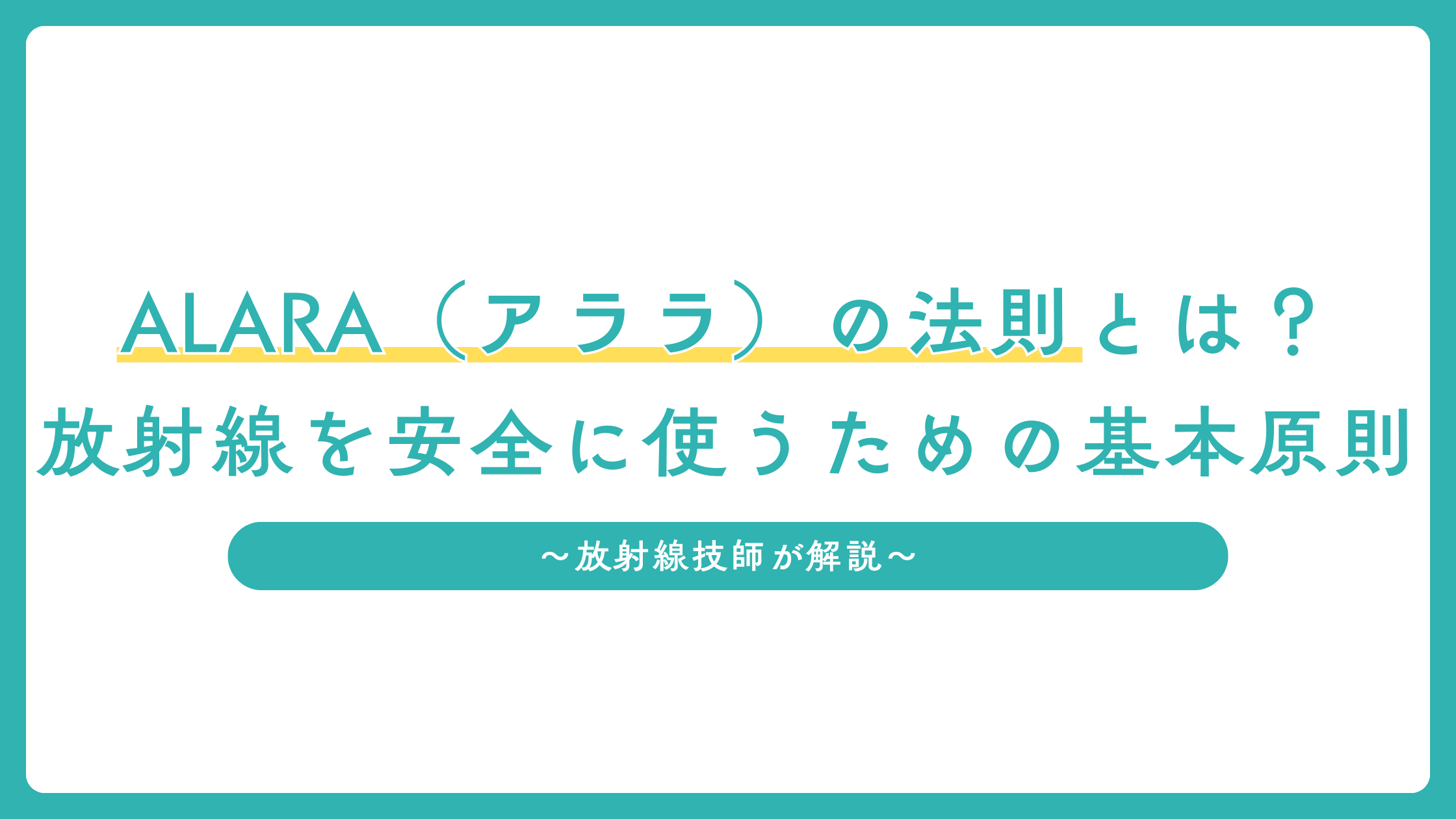
こんにちは。放射線技師のPotetoです。
医療現場では、CTやレントゲン、透視検査など、多くの検査で放射線を使っています。
そんな中で、私たち放射線技師が最も大切にしている考え方のひとつが、「ALARA(アララ)の法則」です。
今回は、このALARAの意味と、実際にどのように医療現場で活かされているのかをわかりやすくご紹介します。
ALARA(アララ)とは?
ALARAとは、英語の
As Low As Reasonably Achievable
の頭文字を取った言葉で、「合理的に達成できる限りできるだけ低く」という意味を持ちます。
つまり、放射線を使う必要がある場合でも、できる限り被ばくを少なくする努力を続けることを示す原則です。
この考え方は、国際放射線防護委員会(ICRP)が提唱する放射線防護の3原則のうちの1つで、 「正当化(Justification)」「最適化(Optimization)」「線量限度(Dose Limitation)」の中の“最適化”に当たります。
医療現場でのALARAの実践例
ALARAは単なるスローガンではなく、医療の現場で具体的に実践されています。
以下のような工夫を通して、私たちは被ばくを最小限に抑えています。
- ① 撮影範囲を必要最小限にする:
CTやレントゲンでは、診断に必要な部位だけを撮影します。たとえば腹部CTでも胸部まで含めないよう、撮影範囲を調整します。 - ② 撮影条件の最適化:
被写体(患者さん)の体格や検査目的に応じて、X線の強さや時間を調整します。必要以上の線量をかけないようにプログラムされています。 - ③ 防護具の使用:
鉛エプロン、甲状腺プロテクター、防護衝立などを用い、不要な部位への被ばくを防ぎます。 - ④ 繰り返し検査の適正化:
同じ検査が短期間で重複しないよう、検査履歴を確認し、必要性を医師と相談します。 - ⑤ 小児や妊婦への特別配慮:
年齢や妊娠の有無に応じて撮影条件をさらに下げる、または検査方法自体を見直すこともあります。
なぜ「ゼロ被ばく」ではなく「できるだけ低く」なのか
放射線のリスクを考えると「ゼロにすればいいのでは?」と思う方もいるかもしれません。 しかし、医療では“放射線を使うことで得られる利益”が大きい場合があります。
たとえばCT検査は、体の内部を正確に評価でき、がんや出血など命に関わる疾患を早期に見つけられる検査です。 「放射線を使う=悪いこと」ではなく、リスクとベネフィットのバランスを取ることが重要です。
ALARAは「使わない」ではなく、「使うときは賢く・最小限に」という医療の姿勢を示しています。
放射線技師の視点:ALARAの本当の意味
現場で働く放射線技師にとって、ALARAは“当たり前の意識”です。 検査のたびに、「この撮影は本当に必要か」「この条件で十分か」を無意識のうちに判断しています。
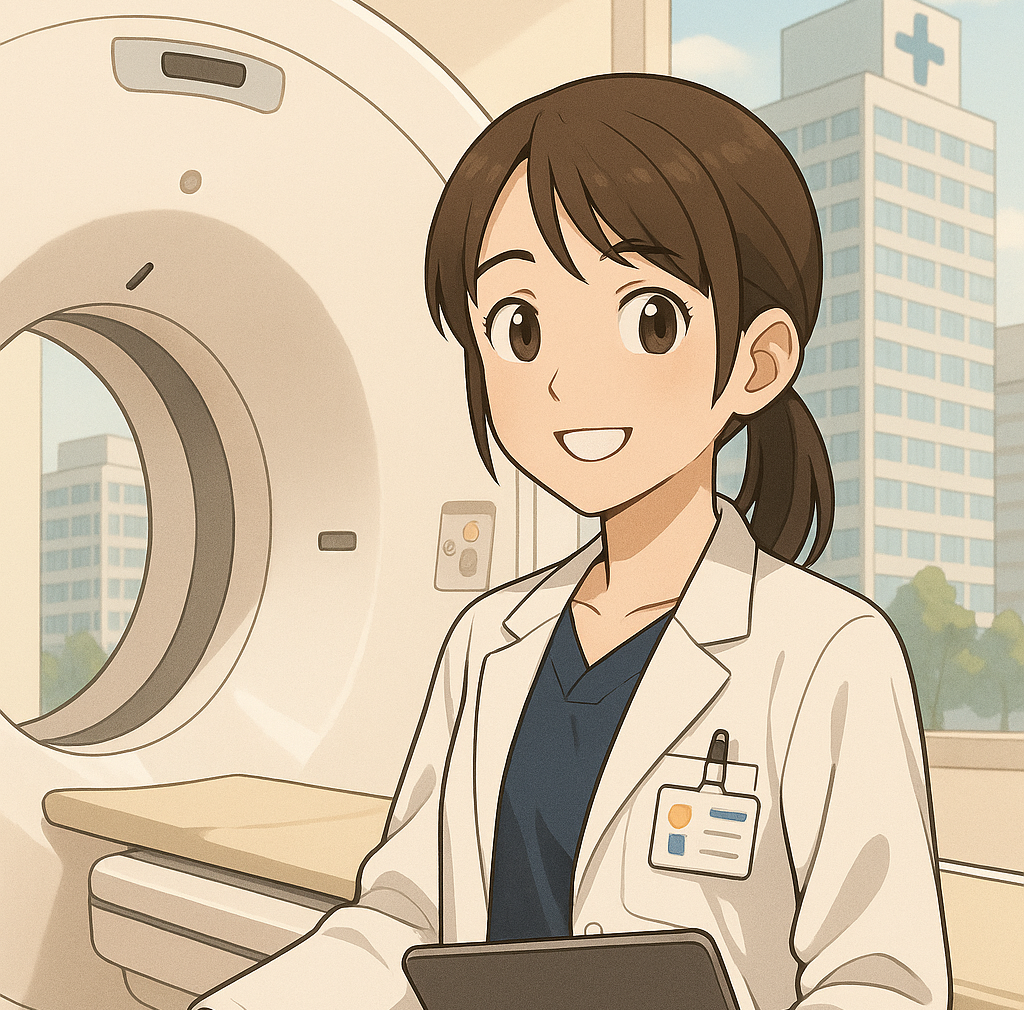
私はこれまで多くの検査を担当してきましたが、同じ検査でも患者さんによって適した条件は異なります。 たとえば、体格の小さい方や子どもでは線量を下げ、体格の大きい方や骨が見づらい高齢の方では少し強めに設定します。 このようにひとりひとりに合わせた最適化こそが、ALARAの実践だと思います。
また、撮影時に患者さんが緊張して体が動いてしまうと、再撮影が必要になり結果的に被ばくが増えてしまいます。 そのため、私たちは「ここで息を止めましょう」「もう少し右を向いてくださいね」など、 患者さんとのコミュニケーションを大切にしています。 ALARAは単に“線量を減らす”だけでなく、「安全で正確な検査を行うための心構え」でもあるのです。
医療被ばくを正しく理解することが大切
医療で受ける放射線量は、国際的な基準のもとで安全に管理されています。 たとえば胸部レントゲンの被ばく線量は約0.05mSvで、これは自然放射線(年間約2.1mSv)のほんの一部です。
つまり、必要な医療検査を受けることによるリスクよりも、病気を見逃すリスクのほうが大きいのです。 ALARAの原則は、放射線を“怖がるため”ではなく“安心して正しく使うため”の考え方です。
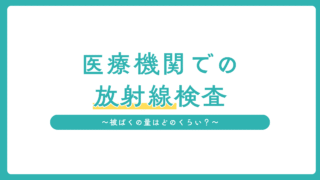
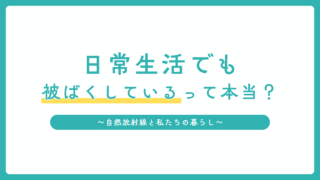
まとめ
ALARA(アララ)の法則は、放射線を扱うすべての医療従事者が守るべき大切な原則です。 「合理的に達成できる限り、できるだけ低く」という考え方のもと、 技師、医師、看護師などが協力して、被ばくを最小限に抑えながら診断や治療を行っています。
放射線技師として私が感じるのは、ALARAとは単なるルールではなく、 患者さんの安全と安心を守る“医療の心”そのものだということです。 これからも「より少ない放射線で、より良い画像を」――その思いで日々検査に取り組んでいます。
参考文献
- ICRP Publication 103(2007)”The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection”
- ICRP Publication 105(2007)”Radiological Protection in Medicine”
- 厚生労働省「医療における放射線防護の考え方」
- 日本放射線技術学会「放射線防護と最適化に関する指針」
- 最終更新日 2025/11/4
- 執筆者 Poteto (診療放射線技師/放射線管理士/放射線被ばく相談員/マンモグラフィ撮影認定技師)
- 免責 本サイトの情報は個別診療に代わるものではありません。