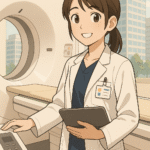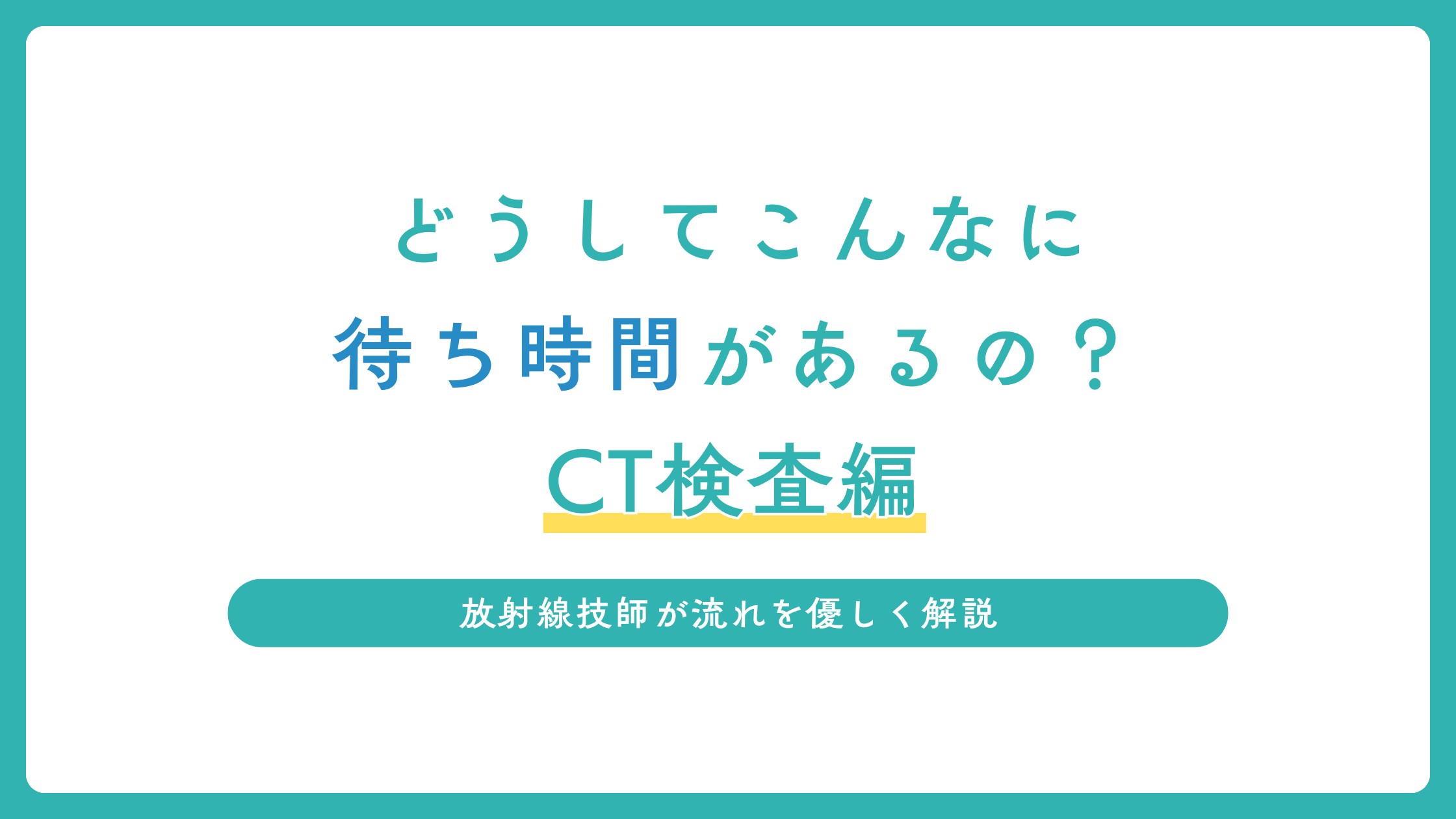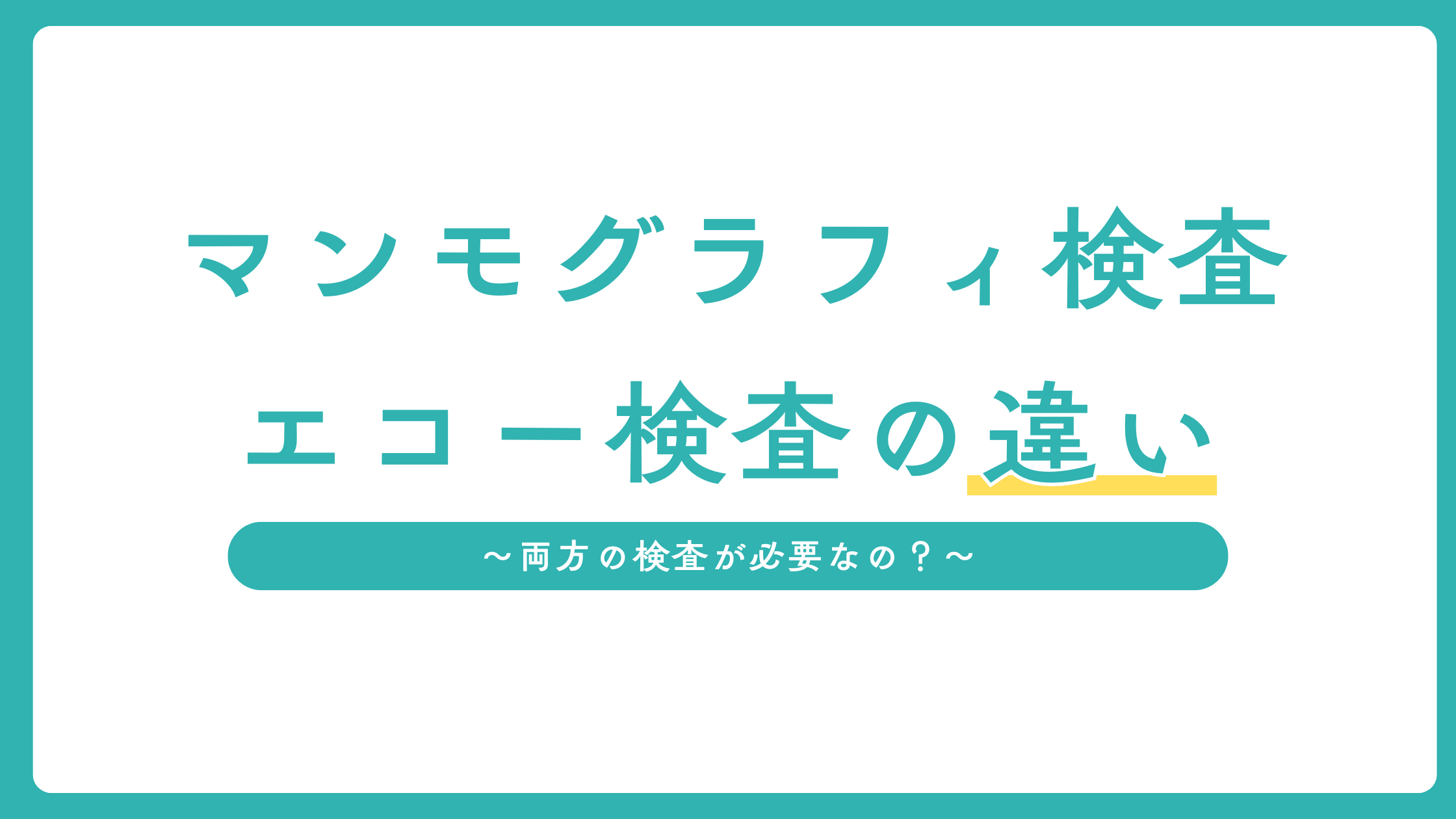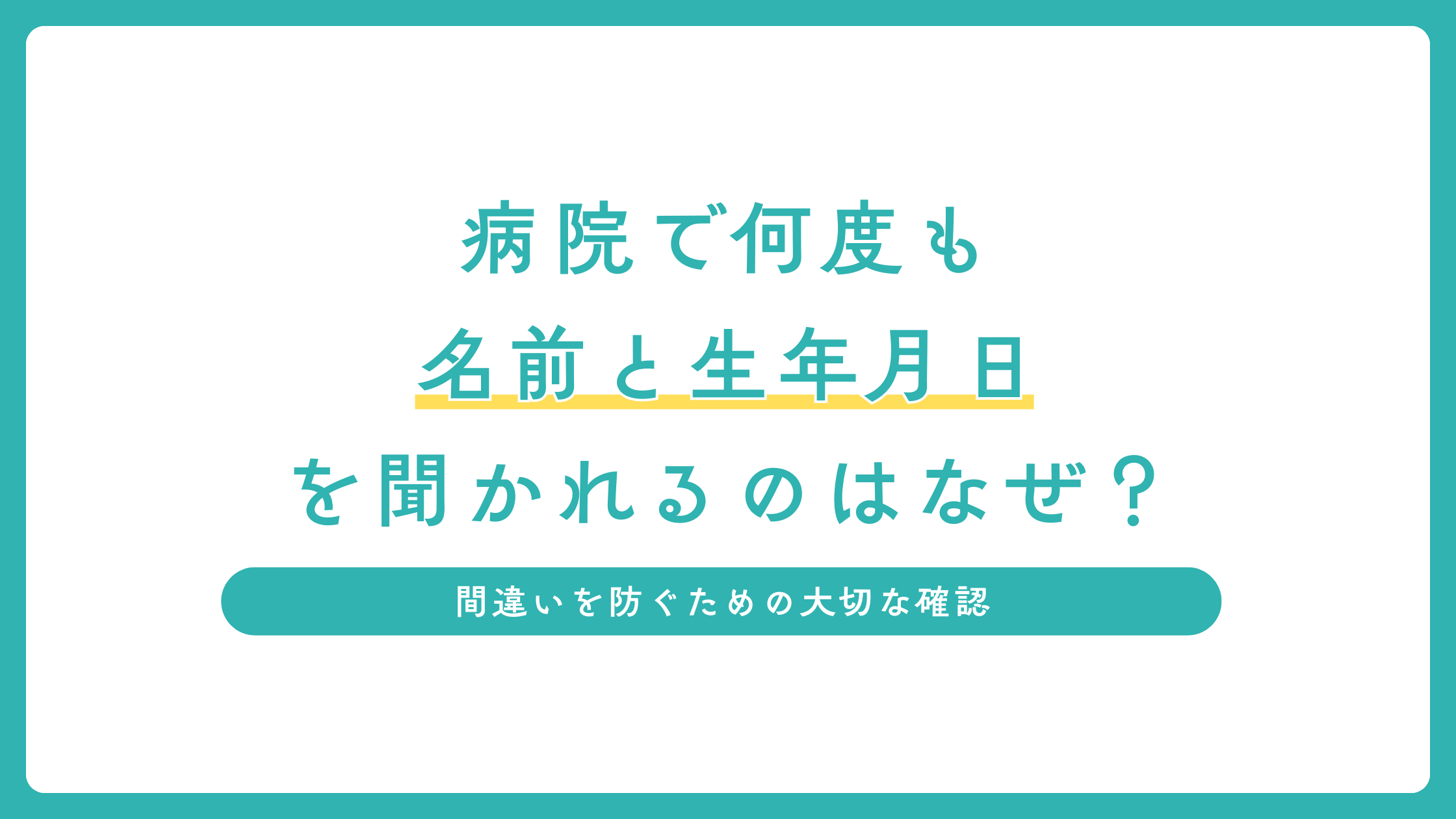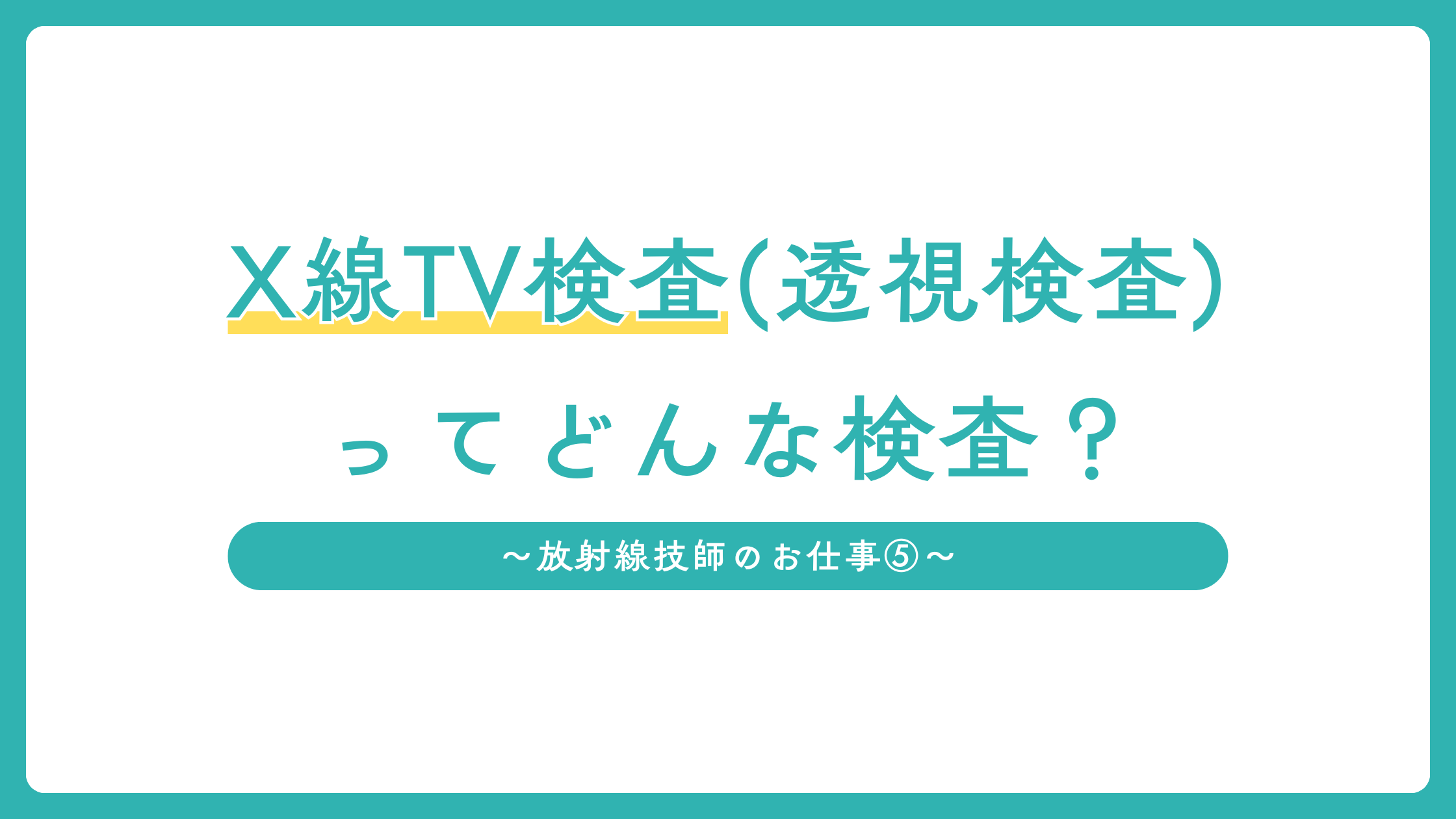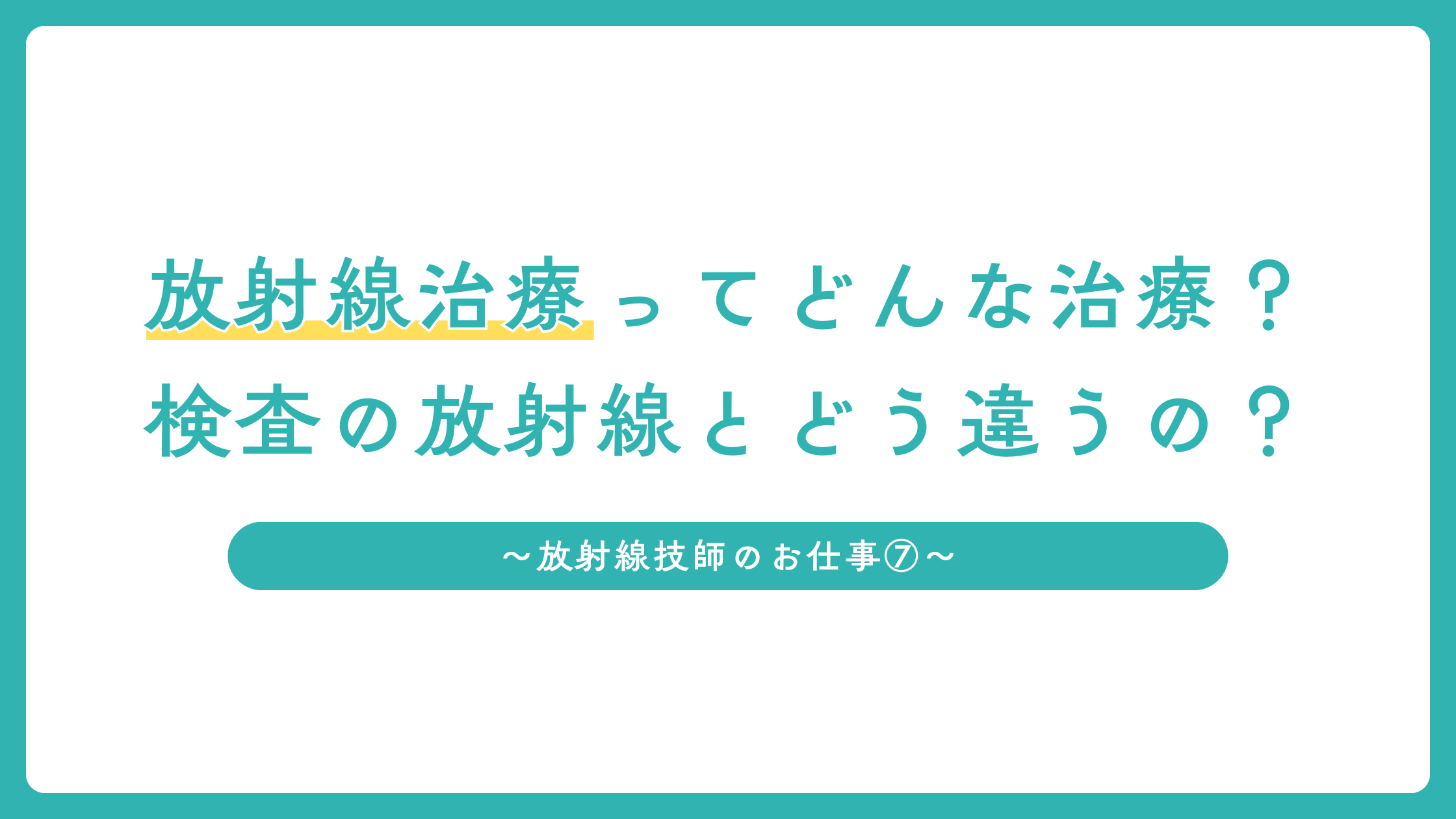骨密度検査ってどんな検査?当日の流れと注意点を放射線技師が解説
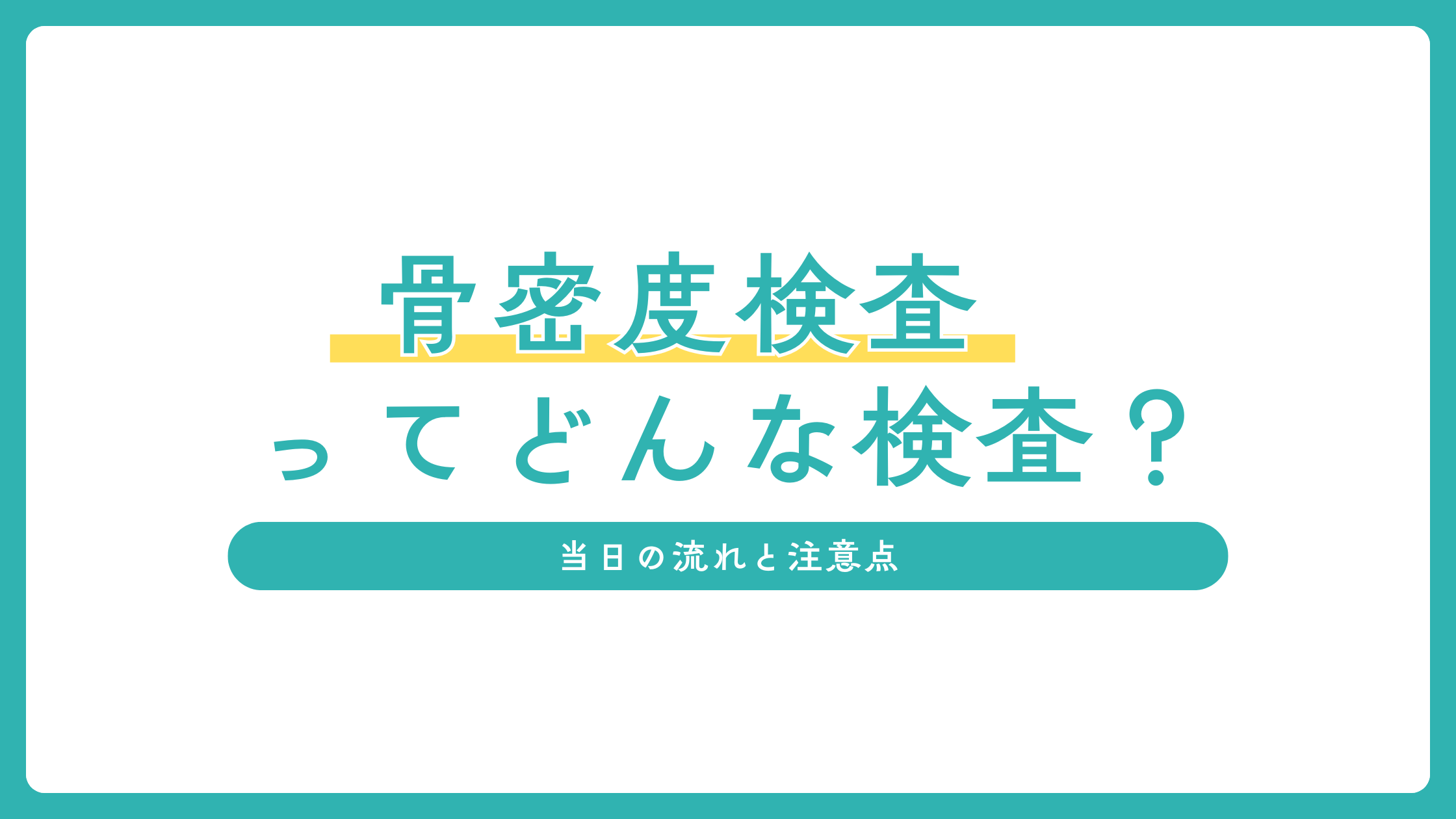
こんにちは。放射線技師のPotetoです。
健康診断や更年期の検査で「骨密度を測りましょう」と言われたことはありませんか?
骨密度検査は、骨の強さを調べる検査で、骨粗しょう症の早期発見や治療効果の判定にとても大切な検査です。
今回は、実際にどんな検査なのか、当日の流れや注意してほしいことを放射線技師の視点からお話しします。
骨密度検査とは?
骨密度検査は、骨の中にどれくらいカルシウムなどのミネラル成分が含まれているかを調べる検査です。
この検査によって、骨がスカスカになっていないか、将来的に骨折のリスクが高くないかを評価します。
現在、最も信頼性が高く使われているのがDXA(デキサ)法と呼ばれる方法で、微量なX線を使って腰椎(腰の骨)や大腿骨(足の付け根)などの骨密度を測定します。
検査の流れ
検査はとてもシンプルで、だいたい10〜15分ほどで終わります。以下のような流れで進みます。
- 受付・準備:検査部位に金属が含まれる衣類やアクセサリーを外していただきます。
- 測定部位の決定:通常は腰や足の付け根(大腿骨)を測定します。必要に応じて腕の骨などを測る場合もあります。
- 撮影台に寝て測定:ベッドのような台に横になり、装置が体の上をゆっくり動いて測定します。痛みや違和感はありません。
- 測定終了:検査が終わったらすぐに普段通りの生活が可能です。
検査のときに気をつけてほしいこと
金属類は外しておきましょう
測定する部位(腰・太もも・腕など)に金属がついていると正確に測定できません。
ベルト・ファスナー・ボタン・補正下着・ネックレス・時計などは、検査前に外しておくようにしましょう。
金属はX線を通さないため、画像に影をつくり、測定値が誤って表示されてしまうことがあります。
人工関節や金属プレートが入っている場合は申告を
もし人工関節・骨折後の金属プレート・スクリューなどを体に入れている場合は、必ず技師に伝えてください。
その部位では正確な測定ができないため、左右どちらか反対側で測るなど、適切に対応します。
申告がないと誤差が生じる可能性があるため、検査の精度に関わる大切なポイントです。
検査中は動かないように
測定中に体を動かすと、画像がぶれて正しい結果が出ないことがあります。
撮影台はゆっくり動くだけなので怖がる必要はありません。
「今から測りますね」などの声かけを行いますので、その間はリラックスして静かにしていてくださいね。
放射線の心配は?
DXA法で使うX線の量はごくわずかで、胸部レントゲンの約1/50以下とされています。
そのため、被ばくの心配はほとんどありません。妊娠中や妊娠の可能性がある方は、事前に申し出ていただければ検査を延期するなどの対応をします。
よくある質問:「骨折しているかわかりますか?」
よく「骨密度検査で骨折もわかりますか?」と聞かれることがあります。
この検査は骨の“密度”を測るものであり、レントゲンのように骨の形やヒビを詳しく見るものではありません。
使用しているX線が非常に弱いため、画像はやや荒く、骨折の診断には適していません。
目的は「骨がどのくらい丈夫か」を数値として評価することです。
まとめ
骨密度検査は、痛みもなく短時間で行える安全な検査です。
正確な結果を得るためには、金属を外す・人工関節などを申告する・動かないという3つが大切です。
検査結果は骨粗しょう症の早期発見に役立ち、将来の骨折リスクを減らす第一歩になります。
気になることや不安な点があれば、遠慮なく放射線技師にご相談くださいね。
参考文献
- International Society for Clinical Densitometry (ISCD). 2023 Official Positions.
- 日本骨粗鬆症学会. 骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン 2023年版.
- 厚生労働省「骨粗しょう症予防と検査について」
- 日本放射線技術学会「DXA法による骨密度測定マニュアル」
- 最終更新日 2025/10/05
- 執筆者 Poteto (診療放射線技師/放射線管理士/放射線被ばく相談員/マンモグラフィ撮影認定技師)
- 免責 本サイトの情報は個別診療に代わるものではありません。