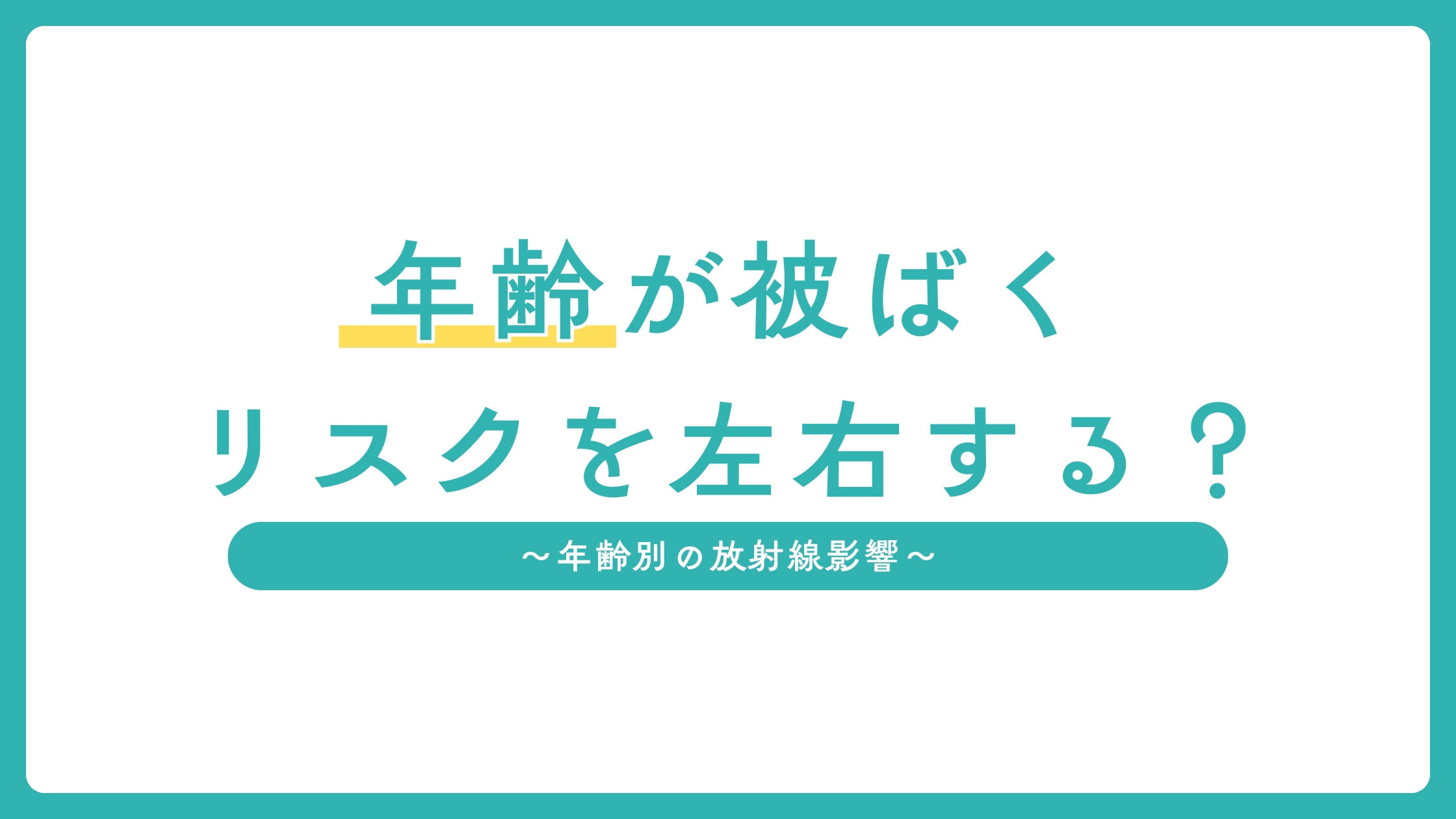Poteto
こんにちは。放射線技師のPotetoです。
「子どもは大丈夫?」「大人や高齢の方はどうなの?」と、年齢による放射線の影響について心配される声をよくいただきます。今日は、年齢と被ばくの関係をやさしく整理してお伝えしますね。
まずは要点
・年齢によって放射線の影響の受けやすさは変わります。
・とくに胎児や小児(0〜14歳)は影響を受けやすいため、検査はより慎重に行います。
・成人(おおよそ20〜64歳)では相対的に感受性が低くなり、高齢(65歳以上)ではさらに小さく評価されます。
・どの年代でも、検査は必要最小限の線量に調整されます。
胎児期(妊娠中)
- 胎児は発育の途中にあり、細胞分裂が盛んなため影響を受けやすい時期です。
- 妊娠初期は器官形成の大切な時期で、撮影部位や必要性を慎重に判断します。
- 医療で行うX線検査やCTは、必要性を満たす範囲で最小限の線量に調整されます。心配なときは、撮影部位・週数・代替手段を一緒に検討しましょう。
小児期(0〜14歳)
- 成長中で細胞分裂が活発なため、同じ線量でも大人より影響が残りやすいと考えられています。
- 小児のCTやX線は「本当に必要か」を丁寧に見極め、撮影する場合も低線量プロトコルで行います。
- 検査の前に、症状・緊急度・他の検査方法(超音波やMRIなど)の選択肢を説明します。
思春期〜若年成人(15〜39歳:AYA世代の目安)
- 体は成熟に向かいますが、将来の累積リスクという観点からも、不要な被ばくは避ける方針です。
- 症状や診療目的に応じて、超音波・MRI・CTなどを適切に選びます。
成人期(おおよそ20〜64歳)
- 成長が終わり、相対的に感受性は小児より低くなります。
- 一方で、診断のメリットが大きい状況(外傷・急性腹症・脳卒中疑いなど)では、迅速で適切な検査が推奨されます。
- 同じく「必要最小限」が基本で、検査条件は体格や目的に合わせて最適化されます。
高齢期(65歳以上)
- 細胞分裂のスピードがゆるやかで、放射線による発がんリスクは相対的にさらに小さく評価されます。
- むしろ病気の早期診断・治療の利益が大きい場面が多いため、必要に応じて適切な検査を行います。
よくある質問
- 放射線は体に残りますか?
残りません。放射線は通り抜けるか吸収されて終わります。体に残るのは「放射性物質」を取り込んだ場合で、そのときは時間の経過とともに減っていきます。
- 子どもの検査は避けたほうがいい?
避けるべきではありません。必要な検査は受けることが大切です。実際には、必要性・代替手段・線量の最小化を丁寧に判断しています。
- 妊娠中の検査は?
撮影部位や週数、症状で方針が変わります。MRIなど放射線を使わない方法の検討も含め、個別にご説明します。
まとめ
- 胎児・小児は影響を受けやすく、検査はより慎重に。
- 成人・高齢では相対的に感受性は低くなる一方、診断のメリットが大きい場面が多くなります。
- 年代に関わらず、検査は必要最小限の線量で行われます。
参考文献
- Little MP, et al. Age effects on radiation response: summary of a recent workshop. 2022.
- Shuryak I, et al. Cancer Risks After Radiation Exposure in Middle Age. 2010.
- Smith-Bindman R, et al. Projected Lifetime Cancer Risks From Current Computed Tomography Imaging. JAMA Intern Med. 2025.
- Ali YF, et al. Cancer Risk of Low Dose Ionizing Radiation. Frontiers in Physics. 2020.
- Tong J, et al. Aging and age-related health effects of ionizing radiation. 2020.
- Dracham CB, et al. Radiation induced secondary malignancies: a review article. 2018.
- Little MP. Review of the risk of cancer following low and moderate exposure during in utero or early childhood. 2022.
- 最終更新日 2025/9/23
- 執筆者 Poteto (診療放射線技師/放射線管理士/放射線被ばく相談員/マンモグラフィ撮影認定技師)
- 免責 本サイトの情報は個別診療に代わるものではありません。
ABOUT ME
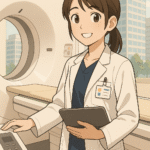
総合病院に勤務している放射線技師のPotetoです!放射線に関する不安や疑問に寄り添うために、このブログを立ち上げました。日々の生活に役立つ放射線の知識や、放射線技師の仕事についてわかりやすく発信しています。